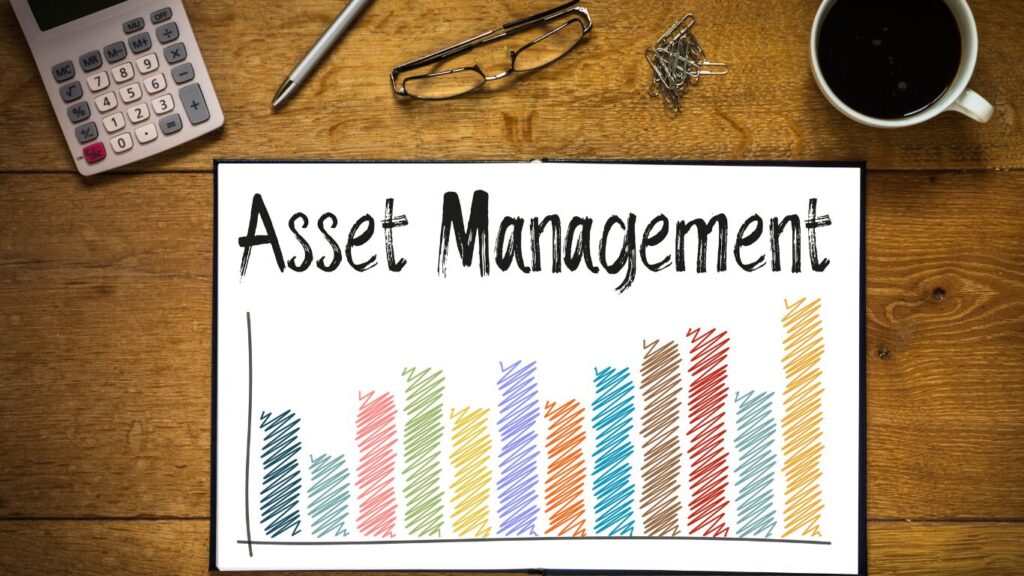アジアには、今後有望な株式市場を持つ国がいくつもあります。
個人投資家にとって魅力的なのは、経済の高成長とテック分野の伸びが期待できる国々です。

本記事では、その中から5つの国を選び、各国の背景、現在の株式市場の状況、注目セクター(特にテック関連)、今後の展望、そして投資リスクや注意点についてわかりやすく解説していきたいと思います。
Contents
インド:世界第3位経済への躍進

インドは人口14億を超えるアジア最大の民主主義国家で、近年著しい経済成長を遂げています。
特に注目すべきは経済規模の拡大で、2027年には日本やドイツを抜いて世界第3位の経済大国になると予想されています。
GDP成長率は毎年6~7%程度と高水準で推移しており、新興国のみならず先進国と比べても群を抜く成長が見込まれています。
若い労働力(人口の中央値は約28歳)と拡大する中間層が、この成長を支える原動力です。」
株式市場の状況
インドの株式市場(代表的な指数にSENSEXやNIFTY50があります)は過去数年で力強いパフォーマンスを見せています。直近5年間では、インド株は世界的な株価下落局面でも底堅さを発揮し、米国株を上回る勢いで上昇しています。例えば2022年や2024年の夏にグローバル市場が下落した際も、インド株式は相対的に下げ幅が小さく、主要国株式と比べ堅調さが際立ちました。これは内需主導の安定した経済成長や企業業績の伸びが株価を下支えしているためです。また、ITサービスや金融など有力企業が多く上場しており、これらの企業が株式指数を牽引しています。
注目セクター
テック産業を中心に多彩。インドと言えばまずIT・テクノロジー分野が挙げられます。世界有数のITサービス企業(例えばTCSやインフォシス)が拠点を置き、ソフトウェア開発やビジネスプロセスアウトソーシングで世界市場をリードしています。またスタートアップも活発で、電子商取引(Flipkartなど)やデジタル決済、AI・ソフトウェア開発の分野でユニコーン企業が続々誕生しています。政府も「デジタル・インディア」政策でITインフラ整備や電子政府化を推進し、テック分野の成長を後押ししています。このほか、再生可能エネルギー(太陽光発電の導入拡大など)も重点分野です。人口増によるエネルギー需要の高まりに対応すべく、クリーンエネルギーや電気自動車関連の投資が増えています。さらに製造業では政府主導の誘致策(スマートフォン製造への優遇措置など)により、ハイテク製造拠点としての地位向上も図られています。
今後の展望
インドの先行きは明るいと見る向きが多いです。高い経済成長を背景に企業の利益も拡大が続く見通しで、株価のさらなる上昇が期待されています。特にテック分野では国内市場の拡大と輸出競争力の向上が見込まれ、ITサービス企業や通信・Eコマース企業の成長余地は大きいでしょう。また政府の経済改革(法人税率の引き下げやインフラ投資拡大など)も民間投資を促進する要因です。加えて、インド株式市場は時価総額で世界上位にありながら国際的な株価指数に占める比率は意外と低く、今後世界の機関投資家がアロケーションを増やすことで追加資金流入の余地もあります。
投資リスク・注意点
インドへの投資で注意すべきは株式のバリュエーションが相対的に高めなことです。成長期待の高さから株価収益率(PER)が他の新興国より高水準で推移する傾向があり、楽観的な見通しが崩れた際には調整もあり得ます。またインドはエネルギー資源を多く輸入しているため原油価格や為替変動の影響を受けやすく、インフレ率の上昇や経常赤字の拡大が投資マインドに影響する可能性があります。政治的には現在安定していますが、選挙の結果次第で経済政策に不透明感が生じるリスクもゼロではありません。加えて、インド市場は外国人投資家に比較的開放されていますが、一部業種では規制が残る点や手続き面の煩雑さにも留意が必要です。
ベトナム:躍進する「アジアの新星」

ベトナムは近年「アジアの新星」として脚光を浴びる新興国です。
1986年のドイモイ(刷新)政策以来、市場経済を導入したことで急速な工業化・経済成長を遂げました。
かつては最貧国の一つでしたが、今や一人当たり所得約4,500ドルの中所得国に成長しています。
若く勤勉な人口と安定した政治体制の下、製造業を中心に海外直接投資(FDI)を惹きつけてきました。
特に中国プラスワンの受け皿として多国籍企業の製造拠点が集積し、スマートフォンや家電製品の輸出が急増しています。
株式市場の状況
ベトナムの代表的な株価指数であるVNインデックスは、中長期的に力強い上昇トレンドを描いています。2023年以降、企業の利益成長に沿って株価指数も上昇を続けており、2025年以降も企業業績拡大が見込まれることから株価もさらなる上昇余地があるとされています。現在のマーケットの株価収益率(PER)はおおよそ8~9倍程度で、過去平均の10倍強を下回っており割安感がある水準です。また、ベトナム株式市場は現在MSCIやFTSEではフロンティア市場に分類されていますが、近い将来、新興国市場への格上げが期待されています。もし外国人投資家に対する株式購入規制の緩和などが進めば、グローバルな資金流入が増えて市場の一段の発展につながるでしょう。
注目セクター
テクノロジー分野の成長が際立ちます。ベトナム政府はIT産業の育成に力を入れており、ソフトウェア開発やモバイルアプリ分野で優秀なエンジニアが台頭しています。実際、ソフトウェア受託開発やアウトソーシングでベトナム企業は存在感を増しており、国内最大手FPTコーポレーションは東南アジア有数のIT企業に成長しました。また通信インフラも着実に整備され、5Gの展開やスマートシティ構想も進行中です。製造業テックでは、サムスンやインテルといった大企業がベトナムに工場を構え、電子機器の生産拠点としても地位を確立しています。さらに、再生可能エネルギーにも注目です。国策として太陽光・風力発電の拡大を掲げ、多くのプロジェクトが進行しています。豊富な日射量と海岸線を活かしたクリーンエネルギー開発は、将来的に電力輸出産業に育つ可能性もあります。この他、成長する中間層に支えられて小売・消費財セクターも活況です。都市化と所得向上に伴い、消費財やサービスへの需要が増えており、多角経営コングロマリット(ビングループなど)が小売・不動産からテックまで幅広く事業を展開しています。
今後の展望
ベトナム経済の先行きは総じてポジティブです。2023年に一時成長が減速したものの、その後は回復基調にあり2024年のGDP成長率は7.1%と予想以上の高い伸びを示しました。2025年はやや成長率が緩やかになるとの予測(5~6%台)もありますが、これは世界経済の不透明感による一時的な調整と見られています。中長期的には旺盛な国内消費、安定した輸出競争力、そして政府の産業育成策によって年率6%程度の成長を維持するとの見通しです。株式市場に関しても、外国人投資家の参加拡大や年金基金など長期資金の流入が期待できます。将来的にMSCI新興国指数への組み入れが実現すれば、ベトナム市場への国際的な資金流入は大幅に増えるでしょう。その意味で、「今は小さい市場だが将来の伸びしろが大きい」典型と言えます。
投資リスク・注意点
ベトナム投資で留意すべきは、市場の透明性と流動性の課題です。新興市場ゆえに情報開示や会計の質にばらつきがある場合があり、個別株投資では十分な調査が必要です。また時価総額が小さい分、株価変動が急激になるリスクもあります。政治面では共産党一党支配による安定がメリットである反面、政府方針の急な変更や汚職摘発による経済への影響もゼロではありません(実際、不動産開発企業に対する規制強化が一時クレジット市場を冷やした例もあります)。さらに貿易依存度が高いため、世界景気の変動や主要貿易相手国の動向に大きく左右されます。中国向け輸出や欧米向け需要が減少すると輸出産業が打撃を受ける可能性があります。為替面ではベトナムドンは安定傾向にありますが、周辺国通貨の下落時には連動安する可能性もあるため注意が必要です。
インドネシア:安定成長する東南アジアの巨人
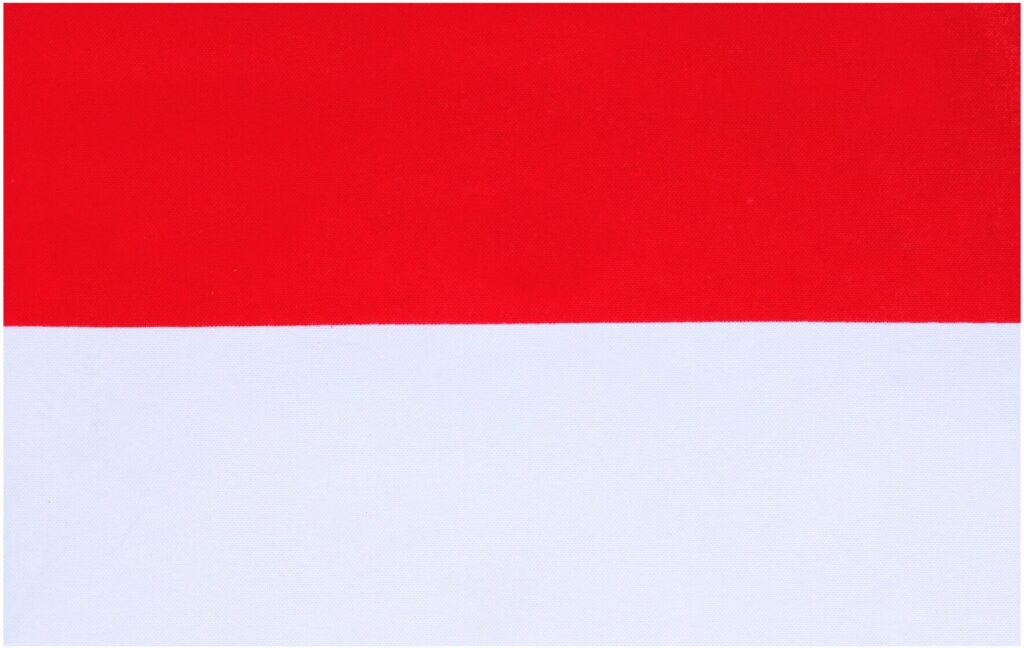
インドネシアは人口約2.8億人を擁する東南アジア最大の経済国です。その経済は石炭・ニッケルなどの豊富な天然資源と、自動車・消費財などの多様な産業基盤に支えられています。
過去10年以上にわたり安定して年5%前後の経済成長を遂げており、コロナ禍からの回復後も2023年に5.05%、2024年も5.03%の成長と堅調なペースを維持しました。この成長率は先進国に比べると高めですが、インドやベトナムのような急成長国に比べると穏やかで「安定感のある成長」と評価されています。政治的にも民主主義が根付き、近年は政権交代も平和裡に行われるなど投資環境の安定性が増しています。
株式市場の状況
ジャカルタ証券取引所の総合指数(JCI)は長期的に見ると右肩上がりの傾向で、過去10年で倍以上に成長してきました。インドネシア株式は伝統的に銀行・財閥系企業や資源関連株が中心ですが、近年は新興のテック企業も上場して話題を呼びました。例えば、配車サービス大手とEC大手が合併したGoToグループや、ECのブカラパックなどが上場し、市場に厚みを与えています。2021~2022年頃にはこれら新興企業のIPOブームも見られました。株価指数は国内消費の拡大や資源価格の動向に連動する面が強く、足元では資源高の一服もあってやや伸び悩む場面もあります。しかしインドネシア市場はMSCI新興国指数にも組み入れられており、国際分散投資の一角として一定の資金流入が続いています。実際、インドネシアの経済成長率は長年5%前後で安定しており、政策金利引下げなど景気下支え策への期待もあって、市場の先行きには明るさが感じられます。
注目セクター
ンドネシアで見逃せないのはデジタル経済の急成長です。政府が「Making Indonesia 4.0」というロードマップを策定し、デジタル産業を国家戦略の柱に据えています。その結果、インドネシアのデジタル経済規模は2025年までに1,300億ドルを超え、東南アジア全体の約44%を占めるとの予測もあります。具体的には、Eコマースがデジタル経済収入の最大シェアを占め、オンラインショッピング利用者の増加で市場は今後も拡大が見込まれます。TokopediaやShopee、Lazadaといった国内外のプラットフォームが熾烈に競争しつつ、市場自体を拡大させています。またフィンテックも重要な成長分野で、銀行口座を持たない人々にスマホ決済サービスが普及しつつあります。電子マネーやデジタル融資、保険テックなど多様なサービスが登場し、金融包摂の拡大とともに急成長しています。加えて、インドネシアのユニークな点として**「スーパーアプリ」の存在があります。Gojek(現GoTo)に代表されるスーパーアプリは、配車やフードデリバリーだけでなく決済・通販まで一つのアプリで提供し、生活インフラとなりつつあります。これが新興中間層の消費行動を取り込み、巨大企業へと成長しました。他方、資源・エネルギーセクターも引き続き重要です。インドネシアは世界有数の石炭・ニッケル生産国であり、電気自動車向けのニッケル精錬やバッテリー産業にも力を入れています。政府は鉱物の付加価値向上を狙って精錬事業への投資を推進しており、資源の下流分野での成長も期待できます。また人口増に対応するためのインフラ建設**(高速道路や新首都建設プロジェクト等)も活発で、建設・不動産分野も堅調です。
今後の展望
インドネシアは堅調な内需と若い人口構成(平均年齢30歳前後)により、中長期的にも安定成長が続く見込みです。世界銀行によれば、インドネシアのGDP成長率は2024~2026年に平均5.1%程度を維持すると予想されています。新政権(2024年就任予定のプラボウォ大統領)も年8%成長という高い目標を掲げていますが、足元の見通しでは5%台前半が現実的との見方が多いです。もっとも、追加の構造改革や産業高度化が進めば成長率の底上げも可能でしょう。株式市場に関して言えば、デジタル経済の拡大によって将来的にテック企業が株式指数に占める割合が増大すると考えられます。現在は銀行や資源株が多い指数構成も、次第に新興企業が台頭することで変化していくでしょう。また、インドネシアの株式は依然としてPERが低めで配当利回りも高く、バリュー市場として海外投資家に再評価される可能性もあります。加えて、経済の安定成長が続けば格付け機関による信用格付の引き上げなどポジティブな連鎖も期待できます。
投資リスク・注意点
インドネシア投資で気を付けたいのは資源価格に左右される側面です。好況期には石炭やパーム油などの輸出で外貨を稼げますが、資源安になると貿易収支が悪化しルピア安・インフレ圧力につながる恐れがあります。また財政面では燃料補助金など政府支出が膨らみやすく、財政赤字拡大時には通貨安・金利上昇を招くリスクがあります。さらに法制度面の不透明さも指摘されます。規制の変更や契約履行の確実性といった点で、海外企業・投資家が慎重になる場面もあります(過去に鉱業権益の見直し等が突然行われた例もありました)。政治的には安定していますが、地方分権が進むことで各州の規制差や汚職の問題なども依然残ります。株式市場は相対的に流動性が高いものの、外国人投資家の動向によって指数が振れやすい面もあるので、中長期スタンスで臨むことが望ましいでしょう。
スリランカ:危機からの復興ポテンシャルに期待
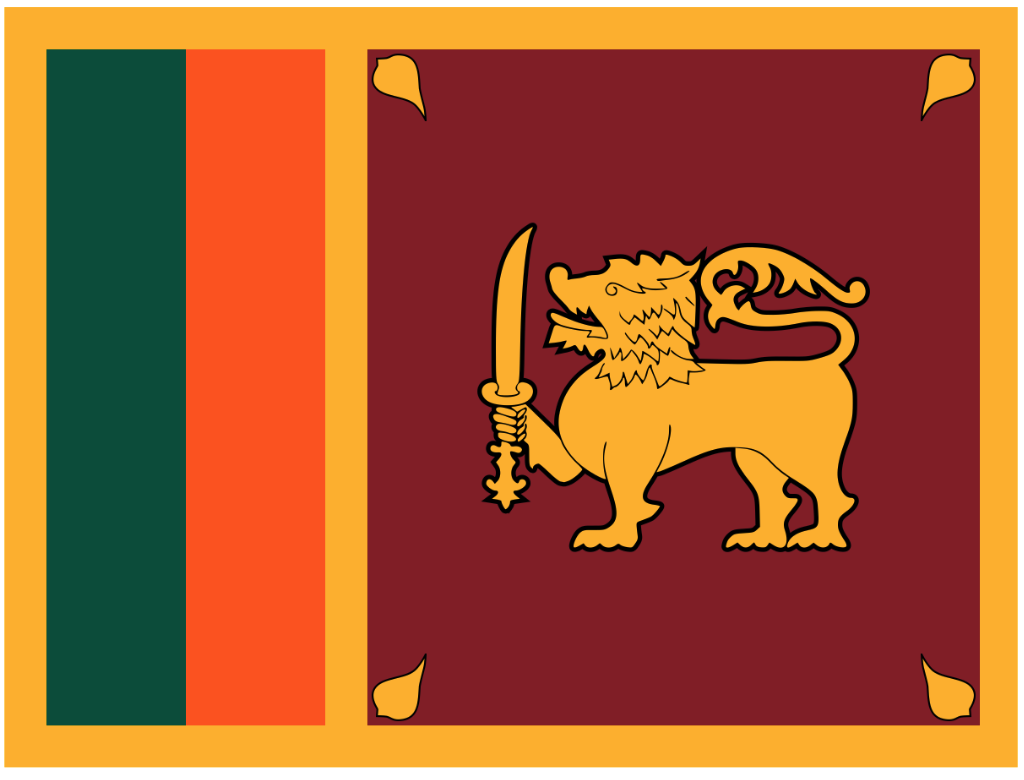
スリランカは他の4カ国に比べ経済規模は小さいものの、大きな経済危機からの復興途上にあるという点で注目されています。
関連:スリランカってどんな国?首都はどこ?人口と言語は?初海外でも安心な魅力と日本文化との違い
2022年に深刻な財政・通貨危機に陥り、同国史上初の対外債務デフォルト(債務不履行)を起こしました。
その影響で経済は2022年にマイナス7.3%という壊滅的な落ち込みとなり、ハイパーインフレと通貨急落に見舞われました。
しかし、その後国際通貨基金(IMF)の支援の下で構造改革に乗り出し、2023年はマイナス成長でしたが下げ幅は-2.3%にとどまり、2024年には年率5%の成長へと急回復しました。
これはIMF予測の4.5%増を上回る「予想外に力強いリバウンド」と評されており、財政再建策や観光業の持ち直しが寄与したと分析されています。
現地でスリランカの成長の勢いを感じたい方はタクシーチャーターで実際に現地にいってみるとよいでしょう。
以下が実際に筆者が利用したタクシーチャーターです。

さらに2024年末までに日本・インド・中国など主要債権国との間で約250億ドルの債務再編(減免・返済猶予)に合意し、デフォルト状態からの脱却に向け前進しました。こうした劇的な転換により、スリランカ経済は「脆弱だが復興の軌道に乗りつつある」と評価されています。
株式市場の状況
スリランカの株式市場(コロンボ証券取引所)は、経済危機の際に外国人資金が大量流出し低迷しましたが、2023年以降は状況が一変しました。2024年には主要指数であるASPI(オールシェア指数)が年間+49.7%、主要20社指数(S&P SL20)も+58.5%という驚異的なリターンを記録しています。これは経済回復期待と通貨安定化を背景に、国内外の投資家が割安な株式を買い戻したためです。実際、2024年には約6,650万ドルの海外からの純資金流入があり、市場に活気が戻りました。また同年には新規株式調達額も過去最高の5億7千万ドルに達し、企業が資本市場で資金を調達する動きも活発化しています。市場バリュエーションを見ると、2024年時点でスリランカ株のPERは約8.9倍とフロンティア市場の中でも最も魅力的な水準に位置しています。デフォルトリスクの軽減や信用格付け改善の見通しもあり、国内市場に対する信頼が徐々に回復していることが伺えます。もっとも、この株価上昇は危機で売られすぎた反動という面もあるため、一巡後は企業業績に見合った適正水準へ落ち着くとの見方もあります。
注目セクター
スリランカで期待されるセクターとしてまず挙げたいのはIT・ビジネスサービス分野です。同国は高い教育水準と英語力を持つ人材が豊富なため、ITアウトソーシングやソフトウェア開発で存在感を高めています。政府もデジタル経済戦略を掲げており、ICT産業を2024年までに年30億ドル規模、2030年には150億ドル規模に成長させる計画を進めています。具体的にはIT企業750社、スタートアップ1500社を国内に育成する目標を掲げ、起業支援やプログラミング教育に注力しています。既に2022年時点でICTサービス輸出は15億ドルに達し、紅茶や繊維に次ぐ第4の外貨獲得源となりました。またスタートアップ・エコシステムも徐々に台頭してきました。2024年の調査によれば、スリランカのスタートアップ生態系の評価額は2億5,200万ドル規模に達し、フィンテックやヘルスTech、教育Techといった分野で有望企業が生まれています。特に政府系アクセラレーターなども設立され、起業家育成の土壌が整いつつあります。伝統的な分野では、観光産業が外せません。長引くコロナと治安不安で打撃を受けましたが、美しいビーチや世界遺産を擁する観光立国としてのポテンシャルは依然高いです。欧米やインドからの観光客は2024年後半から戻り始めており、観光業の復活はサービス業全体のテコ入れにつながるでしょう。農業・プランテーション(紅茶やゴム生産)も雇用の受け皿として重要ですが、こちらは国際価格や天候に左右されやすいため、経済の多角化が課題となっています。
今後の展望
スリランカの今後については「脆弱ながらも希望が見える」というのが率直なところです。IMFは2025年・2026年の成長率を年3%程度とやや控えめに予測していますが、これは危機からの反動増が一巡した後、持続可能なペースに落ち着くという意味合いです。一方で、債務再編の成功と構造改革の継続次第では成長率が上振れる余地もあります。例えば財政赤字の削減と投資環境の改善が進めば、海外からの直接投資が製造業や観光インフラに流入し、潜在成長力を押し上げるでしょう。現に、中東やアジアの投資家がスリランカの港湾開発や工業団地に興味を示す動きも報じられています。また外国人投資家の再評価も進んでいます。2025年3月にはコロンボで「Invest Sri Lanka」投資フォーラムが開催され、世界中の機関投資家・ファンドマネージャーが集まりました。これは政府・中央銀行高官も出席してスリランカ市場の復興ストーリーをアピールする場となり、国際金融界からも「もう見放せない」との声が出ています。こうしたイベントを契機に、新興市場ファンドなどが徐々にスリランカ株式への投資配分を増やす可能性があります。
投資リスク・注意点
スリランカへの投資はハイリスク・ハイリターンの側面があります。最大のリスクはやはり債務問題の再燃です。巨額の対外債務は一旦再編されましたが、今後も財政規律を守りつつ経済成長させないと債務比率は再び悪化しかねません。IMFも税収拡大や歳出削減の継続を強く求めており、仮に政情不安や選挙で改革が滞れば投資家の信認が揺らぐでしょう。また通貨ルピーの信頼回復も道半ばで、依然として高インフレリスクや為替変動リスクがつきまといます。政治的には2024~2025年に予定される選挙の行方が不透明要因です。長年続いたラージャパクサ氏族支配から新体制へ移行しましたが、国民の不満は依然強く、政局の安定性には注意が必要です。さらに小国故に外部環境の影響を受けやすい点も挙げられます。主要輸出先である米欧の景気動向や、隣国インドの経済状況次第では観光・輸出収入が変動し、それが企業業績に波及します。総じて、スリランカは将来の高リターンを狙うフロンティア投資としては魅力的ですが、その分リスク管理と長期目線が求められると言えるでしょう。
おわりに:有望市場への投資にあたって
以上、アジアで今後株式市場が有望と考えられる5つの国を紹介しました。それぞれ経済成長率が高く、テックセクターの伸びが期待できるという共通点があります。インドは巨大市場とIT大国として安定成長が見込まれ、ベトナムは「次の中国」として製造業とデジタル分野で躍進中です。インドネシアは東南アジアの雄として堅調な内需と豊富な資源に支えられ、フィリピンは若い人口とサービス産業で高成長を維持しています。スリランカは特殊なケースですが、危機後のリバウンドと改革への期待からポテンシャルが注目されています。
もっとも、これら新興国への投資は高いリスクも伴います。政治・経済の不確実性や通貨変動、流動性の低さなど、先進国投資にはない注意点が多々あります。それぞれの国の事情に精通し、分散投資や長期視点で臨むことが肝要です。幸い、現在は投資信託やETFを通じて簡便に新興国市場へアクセスする手段も充実しています。個人投資家の皆さんも、専門的なデータを参照しつつカジュアルな気持ちで(しかし油断なく)これら有望市場をウォッチしてみてはいかがでしょうか。将来の成長の果実を享受できるチャンスが、アジアには広がっています。
参考文献・出典: 本記事の内容は各種信頼できる情報源に基づいています。具体的なデータや引用については、文章中の【】内に示したリンク先(レポートやニュース記事等)をご参照ください。それらにはGDP成長率や市場動向、政府の方針などに関する詳細な情報が記載されています。新興国市場は日々状況が変化しますので、最新情報のアップデートにも努めながら、引き続き投資判断の材料としてご活用ください。